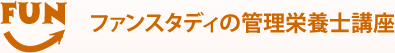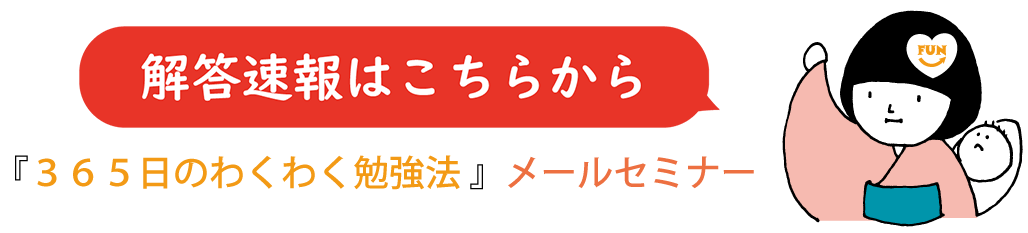2016年 11月 11日
「症例対照研究とか、頭に入らない!」
第31回管理栄養士国家試験まで、あと128日
昨日のメルマガをお読みいただき
多くの方から、週末の計算問題セミナーにお申込みいただきました!
ありがとうございます!!
さて、メルマガでしっかりと予習されて来てください。
昨日のメルマガの続き、疫学研究について学びましょう!
テストの答えからです!
テスト1
大腸がんと野菜の関係を症例対照研究で調べたいけどどうしたらいいですか?
答え
1.まず、大腸がんの集団(症例群)と大腸がんでない集団(対照群)を集める
↓
2.症例群と対照群の過去の野菜摂取量をチェック
症例群の方が対照群より過去の野菜の摂取量が少なかった!
↓
3.野菜を多く摂ることは、大腸がんを予防する!(根拠を持って栄養指導できる)
テスト2
大腸がんと野菜の関係をコホート研究で調べたいけどどうしたらいいですか?
1.野菜の摂取量が350g以上の人の集団を曝露群、350g未満の人の集団を非曝露群とする
↓
2.曝露群と非曝露群の10年後をみて、曝露群の方が大腸がんになっていない人が多かった
↓
3.野菜を多く摂ることは、大腸がんを予防する!(根拠を持って栄養指導できる)
そう、同じ「大腸がんと野菜の関係を調べる」となっても、
研究方法によって調べ方が違ってくるのです。
ちなみに、テスト1とテスト2のパターン。
どっちの結果の方が信頼できそうですか?
テスト1の場合は、過去の野菜量を聞いています。
でも、過去に食べた野菜量を思い出すとなると、
なかなか正確な数字になりそうに思えません。
その点、テスト2の方は、
これから野菜の摂取量を調べていくので、
テスト1の場合より、正確な数字になりそうです。
だから、エビデンスの質は、
テスト1症例対照研究の場合より
テスト2コホート研究の方が高いと言えます!
・未来だからコホート研究
・過去だから症例対照研究
・過去問に同じようなのが出たから
そんな浅い判断基準で問題を解いていませんか?
昨日もお伝えしましたが、疫学研究の分野は、「理解」が必要な分野です。
暗記だけでは太刀打ちできないことが特徴です。
だから理解しましょう。
今週末の計算問題セミナーで、
疫学研究について学びます!!
さて、最近疫学研究の問題が増えたように思いませんか?
しかも具体例を盛り込んだ考えて解く問題。
私としては今の時代に求められているスキルだからだと思います。
続きは、明日♪
直前のお申込み大歓迎です↓^^