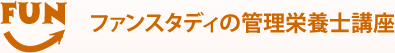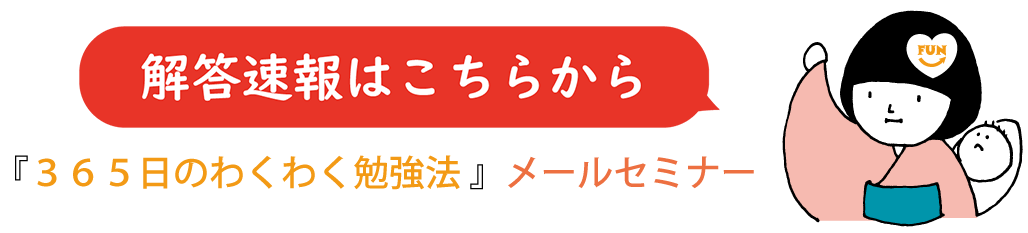2016年
8月
05日
さて、ホルモンマスターの予習をしていきましょう!
●合格と知識維持に本気の方限定で募集!
8月13日ホルモンマスター萩野祐子先生・40名限定(東京都・秋葉原)
8月14日病気を考えて解くセミナー吉田順子先生・40名限定(東京都・秋葉原)
https://eiyousi.net/?p=10964
かなり多く出題されているホルモン!
ポイントはいくつかありますが、大きく分けると3つです!
1.どこから分泌されるのか
2.どんな働きをするのか
3.ホルモンの病気の症状、対策
2.どんな働きをするのか
ホルモンマスターで学ぶ裏ワザを
一部メルマガで公開します♪
脳の下垂体後葉から分泌されるホルモン
バソプレシンの作用の場合
・集合管、遠位尿細管での水の再吸収促進する
・尿を濃縮する
・尿量を減少させる
・血圧を上昇させる
・分泌が低下することで尿崩症となる
・分泌が低下すると体内の水分が不足し、高ナトリウム血症、水分欠乏性脱水症(高張性脱水)、血漿浸透圧上昇となる
・高温環境では、分泌が上昇する
・体水分量不足状態では、分泌が上昇する
・血漿浸透圧が上昇すると、分泌が上昇する
・抗利尿ホルモン不適合分泌症候群(SIADH)となり分泌が上昇すると、体内の水分が増加し、低ナトリウム血症となる
上記のすべては、
「バソプレシン=抗利尿ホルモン」
と、覚えることで考えて解けるようになるのです!
どういう事なのでしょうか!?
抗利尿ホルモンとは
「利尿(おしっこをたくさん出す)」の
逆の言葉です。
例えばバソプレシンの作用の1つ
「血圧を上昇させる」の場合。
バソプレシンは、
おしっこを減らす
↓
ということは、
体内の水分量が増える
↓
ということは、
血液の量が増えて
血圧が上がる
こうやって
考えて解きます。
上記のすべてがこれで解けるということ。
考えて分かりますか?
もっと知りたい方は
ホルモンマスターのPVをご覧くださいね!
https://youtu.be/TGUyBdABJAs
「バソプレシン=抗利尿ホルモン」
このように、ホルモンの働きは、たくさん覚えるのでなく、
考えて解くためのスタートを正しく覚え、考えて解く練習をすることがポイントです!
国家試験に出題されたホルモンの働きのうち、「この1つを覚える!」を、セミナーでは提示し、
考えて解く練習をしていきます♪
明日は、「3.ホルモンの病気の症状、対策」について♪
2016年
8月
04日
本日、素敵栄養士estに参加しに
東京に行き、今、帰りの飛行機の待ち時間です♪
今回のイベントで、パネラーとして登壇させていただき、
「この会場にいらっしゃる、
管理栄養士のみなさんで、
もう一回管理栄養士試験を受けて、合格する自信があるという方、
いらっしゃいますか?」
そう質問させていただいたところ、
なんと、一人も手が挙がりませんでした笑
管理栄養士さんから求められている学習は?という質問に、
私は「まず求められる状態を創りたい」そうお伝えしました。
管理栄養士に合格するまでは、
学習の目的が明確でした。
ですが、一番困ったのは、
合格した後です。
知識は、流れ出ていくばかり。
仕事で使う知識には触れると言えども、
そんなのは、とても小さな範囲。
例えば糖尿病を説明しようとしても
基本的な人体の働きがわかっていないと
説明をすることは、できません。
管理栄養士という資格を取った後は、
その資格をどう使うのか?
人生ゲームで例えると、1つ大きなアイテムが増えた自分。
それをどう生かすのか?
そこから逆算しての、管理栄養士に合格した先の学び。
それに必要な、国家試験レベルの基本的な知識の維持。
伝えていきたいです!
さて、今日素敵栄養士estで出題した、クイズの答えは、こちらです↓
https://youtu.be/_QqyAfBskpI
(栄養士さんも管理栄養士さんも知っておくべき知識です!)
2016年
8月
03日
今日の1日1問
問題:こんにゃく製造の際の凝固に使用されているのは?
答えとゴロソングは、最後♪
昨日のクイズについてです。
食品成分表を見ると、全卵(生)のビタミンAのところには、
レチノール140
αカロテン0
βカロテン3
β-クリプトキサンチン28
β-カロテン当量17
レチノール活性当量150
なんか、こんなにもいろいろと書いてあります。
単位は、μgと書いてあります。
「卵に含まれるビタミンAってどのくらい?」という質問に、
あなたなら、どう答えますか?
食事摂取基準との兼ね合いを考えると、
「レチノール活性当量150」と答えることが正解となります。
では、そもそもレチノール活性当量って何なんでしょう!?
ビタミンAとは、レチノール、レチナール、レチノイン酸などの総称です。
さらに、体内でビタミンAに変換されるものがあります。
それがプロビタミンAです。
プロビタミンAには、β-カロテン、α-カロテン、β‒クリプトキサンチン、その他のプロビタミンAカロテノイド(50種類ほど)があるのです。
プロビタミンAは体内で必要な分だけビタミンAに変換されます。
ただし、プロビタミンAが、すべてビタミンAに変わるというわけではありません。
生体利用率が違うのでそれらを考慮する必要があるのです。
例えば、β-カロテン の場合は、12μg が、レチノール 1μg に相当する、つまりβ-カロテン生体利用率は、レチノールの1/12ということなのです。
これらをまとめて、体内でどれくらいビタミンAのレチノールとして活躍するかを示すのが、「レチノール活性当量(μgRAE)」です。
ただし、この計算式(表し方)は、日本人の食事摂取基準2015年版と
日本食品標準成分表2015年版七訂(以下、食品成分表)で少し違います。
「あー!もう苦手!その話!」という方!
ぜひこの続きは、動画でご覧ください^^
https://youtu.be/_QqyAfBskpI
(栄養士さんも管理栄養士さんも知っておくべき知識です!)
今日の1日1問
問題:こんにゃく製造の際の凝固に使用されているのは?
答え:水酸化カルシウム
これを覚えるゴロ合わせソングは?こちら↓
https://youtu.be/WPuotuUg1NQ